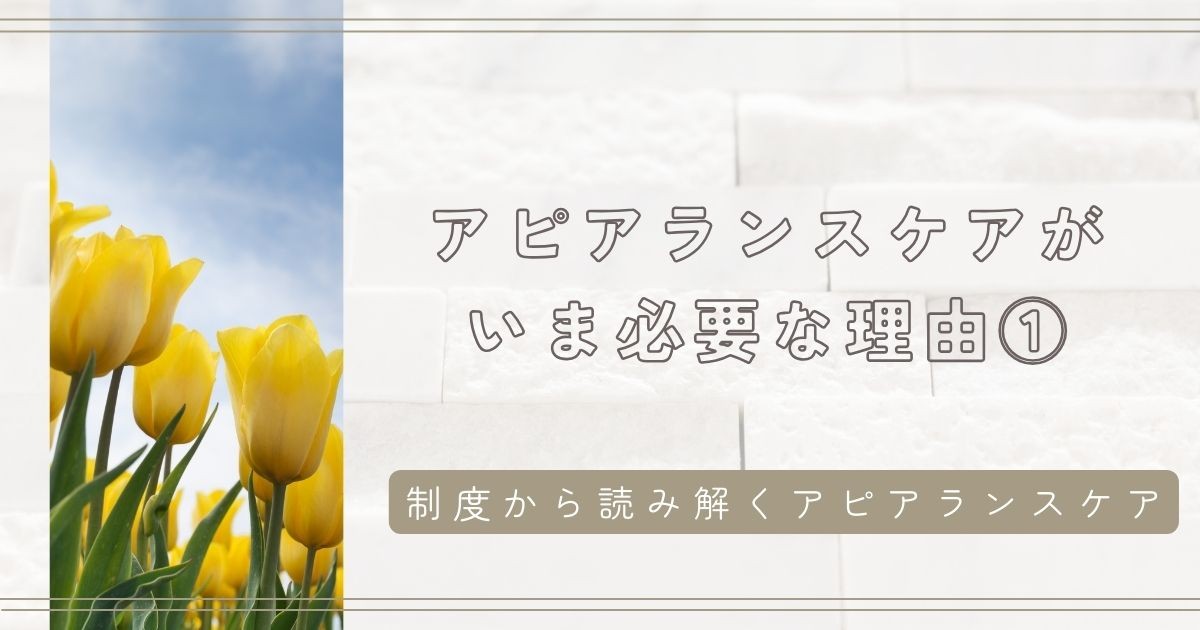看護師経験を活かした、
安心とやさしさのプライベートサロン‐minu(ミヌ)‐
セラピストのRieです
「見た目を整えること」が、ただの美容ではなく、誰かの“生きる力”になることがあります。
治療の副作用で鏡を見るのがつらくなる日も、誰かの手でそっと整えられることで、ふっと心が軽くなる瞬間がある。
私がアピアランスケアという分野に関わるようになった理由、そしてなぜ今このケアが必要とされているのか。
それを、あらためて伝えたくて、今回この投稿を書きました。
今回は、アピアランスケアがなぜ今、医療や社会にとって必要不可欠なのか。
制度や調査データの動きを交えながら、その背景と現状、そして私がこの活動を通して感じている想いについて書いてみました。
アピアランスケアがなぜ必要なのか
私は、アピアランスケアがこれからの世の中に必要不可欠だと感じ、日々活動を続けています。
なぜなら、外見を少し整えるだけで、自分の気持ちがふっと軽くなり、自然と前を向ける力が湧いてくることがあるからです。
「美容には、心を支える力がある」——私はこのことを、これまで多くの方と関わる中で強く実感してきました。
アピアランスケアとは、メイクやネイル、ウィッグだけを意味するものではありません。
それらはあくまで手段の一つであり、本質は「患者と社会をつなぐこと」なのです。
社会的背景と制度的な後押し
日本では、がん治療の進歩により「がんと共に生きる・働く」時代に入りました。
一方で、抗がん剤や手術による脱毛・皮膚障害・傷跡など、外見の変化は患者さんにとって大きな心理的・社会的負担となっています。
実際に、厚生労働省が2018年に行った全国がん経験者調査(全国20歳以上のがん患者3,000名対象)では、がん治療による外見変化を経験した方の約40%が「外出が減った」「人と会うのが億劫になった」と答え、42.5%が「仕事や学校を辞めたり休んだりした」と報告しています。
厚生労働省の取り組みと今後の課題
こうした背景を受け、厚生労働省は2018年の「がん対策推進基本計画」において、初めて「アピアランスケア」の文言を明記し、患者が外見の悩みを安心して相談できる体制の整備を推進しています。
第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定)にて、
「アピアランスケア」が独立した項目として記載されている
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127422.pdf
アピアランスケアに関しては、がん対策基本法に理念として位置づけられ、推進基本計画で具体的な対策が示されています
また、医療者への研修や、がん拠点病院における支援体制の構築なども進められており、アピアランスケアは「美容」ではなく「医療の一部」として捉えられるようになってきました。
しかし現状では、相談体制の不十分さや、医療従事者の認知度の低さといった課題も残されています。
私ができること
病気の治療や副作用によって、
鏡を見るのがつらくなる日があるかもしれません。
そんなとき、誰かの手で
「やさしく整えられる」「気持ちが軽くなる」
そんなケアが心の支えになることがあると、私は信じています。
看護師として医療の現場にいたとき、
命を守ることが最優先で、
患者さんの気持ちや外見の変化に寄り添う時間を取れないこともありました。
だからこそ、今の私ができること。
単なるカモフラージュメイクではなく、
内面と丁寧に向き合うメイクセラピーも学び、実践をしております。
ただ「見た目を整える」だけでなく、その人が心の中で感じている感情に気づき、安心して吐き出せるような場をつくりたいのです。
そして、自分らしく社会の中ですごしてもらいたい。
そんな想いを込めて、minuを始めました。